1月1日の夜遅く、友達のKさんから電話が入る。僧侶の直感か誰かがなくなったのではないかと思った。恐る恐る電話をとってみると、親友のNさんが亡くなったという。Nさんと最後に話したのは、一昨年の10月である。そのときの内容は鮮明に覚えている。
Nさんとは30年来の友である。昨年と暮れにNさんの事がなぜか気にかかり連絡を取ろうと思っていたが、お寺のほうが暮れの忙しさもあってつい連絡を取ることを忘れてしまった。まさか、と思ったが仕方がない。
通夜法要に参列し、Nさんの遺影をいてみると1昨年まで黒界のはずが真っ白になっていたことに驚いた。でも、遺影の表情は元気な時そのままでる。通夜法要が執り行われているとき、ともに旅行にいた時の事や、ともに教職にいたため教育についてともに話し合ったこと、ともに酒を酌み交わしたことなど様々なことが思い出された。
でも、通夜法要に出ているにもかかわらず彼が亡くなったとはどうしても信じられない。私の心の中に生きつけている。これも事実である。人は関わりが深ければ深いほど、心の中に生き続けるということをよく話をするが、これほど深く自分の中に彼が生きてるということを思い知らされたことに自分も驚いている。
身近な人が亡くなると自然と人は手を合わすものである。実はそのことが、人の死を無駄にしないことにつながる。日常生活の中で心から手を合わすということが少なくなってきているように思われる昨今。でも、通夜や葬儀の時は自然と人は手を合わす。その時のことを忘れず、手を合わすということが亡くなったか方から改めて教えられることであり、その人の死を無駄にしないことにつながるのではないかと思うのです。
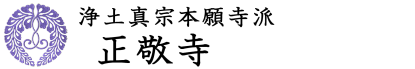

真宗十派と言われるほど、真宗は各派に分かれてる。宗祖は同じ。 しかし、各派は派祖への対応、葬儀などの流儀が微妙に異なる。これから入信する、又は改信する善男善女は、何を基準に各派を選べばよいのか。派の将来性、出会った僧侶の説教、信者の評判、派との相性等、選択する場合のポイントをご示唆ください。
但し、寺請制度で家の宗派は守って来たが、本願寺・大谷派は組織が大きくなり過ぎた。信者のために、更に親しみやすい真宗であることを期待します。
追伸 いろいろの解説は、大変、役立ちました。有難ごさいいました。以上
コメントありがとうございます。
確かに真宗は多くの流派に分かれてますね。
これに関しては、微妙な作法の違いであったり、教えの受け止めが少しずつ違っていたりのようですが、正直なところ、私も何がどう違うのかなど良く知りません。ですので、選択する場合のポイントなどは私からは、申し上げることは出来ません。ご希望に添えず申し訳ございません。
あえて言えば、縁というのも大切なポイントではないかと思います。
何と出会い、何と時間を共にするのかは、自分で選択しているようで、案外偶然が重なって選んでいることが多い気がします。
その偶然は、真宗の模範解答で言えば、「縁のあった菩薩様が導いてくださっている」となるかと思いますが、心の惹かれる選択をされればいいのではないかと思います。
「宗というのはほとけさまの領分 派というのは人間の領分」ということを聞いたことがあります。
同じ親鸞聖人の門徒。
お西さんでもお東さんでも 縁のあったすばらしいお寺や法座に お参りしあっていいのではないかと 私は思います。
西だ東だと 張り合っている時代ではもうないのではないでしょか(私の縁のあるお寺さんでも 大谷派のご門徒さんが来られています)。
作法とか 声明の節とか お内仏の飾り方は 縁に応じて有縁のお寺さんにご指導いただけばいいのではないでしょうか。